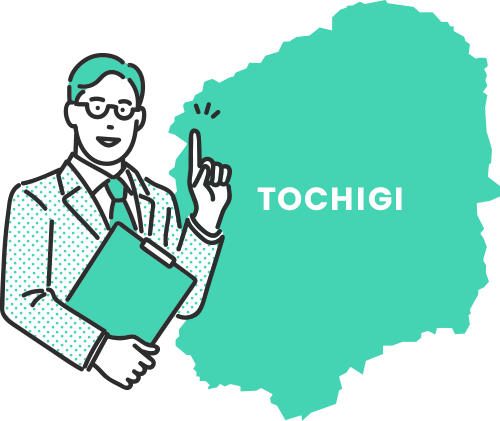人生に立ち止まってみたら、自分らしい暮らしに出会えた
檜澤 しのぶ(ひざわ しのぶ)さん
コロナ禍をきっかけに、新たな人生へ 前職は大手ホテルのセールス担当。新潟にあるホテルの東京営業所に所属し、都内の企業や旅行会社に向けて宿泊や宴会、レストランなどのサービスを案内していた。 「当時は忙しすぎて、立ち止まる余裕なんてなかったですね。売上の数字を常に背負い、お客様の期待値を超える演出をする日々は、やりがいはありましたが、仕事に追われる生活でした。」 そう語る檜澤さん。 立ち止まるきっかけは新型コロナの感染拡大だった。大打撃を受けたホテル業界の例に漏れず、檜澤さんが働く東京営業所も閉鎖されることに。 「良くも悪くも、これが移住を考え始めるきっかけになりました。初めて立ち止まってみて思ったのは、私の人生このままでいいのかなって。じゃあ、思い切って一回全部リセットしてみようと!」 その後、1年間休職。休職中に、以前から興味のあった地方創生や観光について学んだ。 そんな時、縁があり、日本全国の移住支援を行う「ふるさと回帰支援センター」の栃木県窓口の相談員を務める生田さんから、真岡市移住定住コーディネーター募集の案内を受ける。 東京に進学・就職し、地元である真岡市を離れて数十年。新しい人生を送る地は真岡市でいいのか……すぐには決められなかった。 背中を押してくれたのは、地元の友人の言葉だったという。 「今、真岡市の未来のために、行政と大人、学生たちが公民連携で動いているよ。これから真岡市が面白くなる。一緒にやろうよ!」 移住はご縁とタイミング。ふるさとに戻ることに決めた。 ゆるやかな時間、おだやかな暮らし 東京と真岡市では、時間の流れ方が明らかに違う。 競争社会である東京では、自分より他人を優先し、時間に追われる生活だったが、今はワークライフバランスを取りながら自分らしい生活を送れている。 散歩中に見る田んぼや満開の桜並木、緑生い茂る樹木、カエルや鈴虫の鳴き声、キンモクセイの香り―。 何気ない日常の風景から季節が感じられ、自然とともに生きているんだとしみじみ思う。なんとも心地のよい生活である。 東京に住む友人からは「表情がすっきりして顔色がよくなった」と言われた。人は暮らす環境によってメンタルが大きく左右されるのだと身をもって体感した。 「今は、子どもの頃にやってみたかったことにも、どんどんチャレンジしてみたいと思っていて。そんなことを思えるようになった自分にびっくりです。東京ではそんな余裕がありませんでしたから。今は自分の可能性が広がっていくようで、ワクワク感がありますね!」 車の運転も、真岡市に戻ってからするようになった。 確かに、地方は東京ほど便利ではない。ただ、不安に思う必要はないという。 「東京だと車を運転する必要がなかったので、真岡市に戻っても自転車で移動すればいいやと思っていたんですが……自転車で動ける範囲なんて限られていますもんね(笑)父に教えてもらったり、ペーパードライバー向けの講習を受けたりして、運転スキルを上げていきました。今はマイカーも購入して、高速道路も運転できるまでに上達しています。」 都会と比較した際の生活利便性は、多くの移住検討者にとって不安要素のひとつかもしれない。ただ、本当に地方に移住すれば利便性は下がるのだろうか。 「運転できるようになって、私はむしろ移動の自由度が高まりましたね。休みの日はあそこに行ってみようとか、あの人に会いに行ってみようとか、アクティブになりました!確かに新しい一歩を踏み出すのは怖いかもしれませんが、慣れれば問題ありません。今年の冬は、マイカーでスキーに初挑戦する予定です!」 真岡市には十分な数のスーパーがあり、学校があり、総合病院もある。自然も豊かで、子育て世代にも人気のまちとなっている。 地方移住に対する漠然とした不安は、あなたの小さな一歩によって意外と簡単に解決できるのかもしれない。 数十年ぶりの実家暮らしで得た気づき 今は両親・姉家族と9人でにぎやかに暮らす檜澤さん。東京での2人暮らしから、実家での9人暮らしへ。抵抗はなかったのだろうか。 「もちろん、ありました!いまさら両親と暮らすなんて、なんか恥ずかしいと思っていましたから。一人暮らしをしようとアパートを探していたんですが、空いている物件がなかったりで、家族全員に住まわせてください、とお願いしました(笑)」 家業は米農家。現役の父。小顔に映りたい母。 住む場所はもちろん、仕事や周囲の人もすべて変わり、移住して間もなく体調を崩したことがあった。 そんな時、改めて自分を見つめ直すきっかけをくれたのが両親だった。 「体調を崩した時に、両親に相談したんです。そしたら、母からは『しのぶは小さい頃から、ないものねだりだ。今あるものを大事にすればいいの。』父からは『しのぶには信念がない。信念があれば、人に何言われても揺らぐことはない。諦めるな。』と言われて…。被っていた鎧を捨てられた気がします。自分の弱いところも見えたし、かっこつけていたところもわかりました。」 一番近い距離にいる両親からの言葉に、自分らしさを気づかせてもらったという。 真岡市にUターンをして、両親と暮らせてよかった、と笑顔で語るようすが印象的だった。 真岡市の魅力を日本中へ! 真岡市では移住定住コーディネーターとして、移住のお手伝いをする日々。 「移住って大変じゃないですか。仕事も住む場所も、交通手段も気候も友人も……自分の人生全部が一気に変わるので。私自身、体調崩したり、不安があったので、移住定住コーディネーターとして接する時は親身になって相談に乗れるように心がけていますね。移住は覚悟が必要で、人生における大きな決断でもあるので、「希望する生き方」「本音」を聞き出しながら、なるべく真岡市の正確な情報を伝えるようにしています。踏み込んだ話もしっかりと伝えてもらえているのは、話しやすい空気を作れている結果かなと思いますね。」 檜澤さん自身が移住者であるということが、相談する人にとって安心できるポイントになっているのだろう。そして、底抜けに明るく人懐っこい人柄がひと役買っていることは言うまでもない。 真岡市といえば、55年連続いちご生産量1位を誇る「いちご王国・栃木」において、一番の生産量を誇るとともに、いちごの品質や栽培技術を競う「いちご王国グランプリ」においても、最高賞の大賞(農林水産大臣賞)を最多受賞する、まさに「質」・「量」ともに「日本一のいちごのまち」。 真岡市移住定住コーディネーターを務める檜澤さんの目標は、「もおかDEのうか いちご就農するなら真岡市」を全国に広め、いちご就農する後継者を移住者で増やすことだという。 「地方移住して農業を始めたいっていう方のご相談は結構あります。ただ、専門の就農窓口はハードルが高いみたいですね。そんな時に、私がいちごの被り物なんかして移住相談窓口にいると、話しかけやすいみたいです(笑)」 いちご就農した先輩移住者と移住検討者を引き合わせる機会などもあり、人と人をつなぐ仕事なんだと実感することも多い。 「真岡市のいちご農家さんって、『日本一のいちご産地』として誇りと情熱をもっていらっしゃる方が多いんです。後継者や「もおかっ子」の未来を真剣に考えられている方も多くて。そんな方々とお話していたら、私自身も未来の真岡市の担い手になりたいっていう熱い気持ちが湧き上がってくるようになりましたね。」 移住者、つまりは新しい風として、今の仕事を通じて未来の真岡市を盛り上げていきたいという。 「真岡愛溢れる市民がたくさんいるので、一緒に活動ができて本当に楽しいです。」 もおかDEのうか いちご就農するなら真岡市 FMもおかとのコラボで制作したPR音源。 真岡市を象徴する、真岡鐵道のSLの汽笛が懐かしい。地元を離れて暮らす真岡市民や栃木県民に聞いてもらい、ぜひふるさとを思い出すきっかけにしてほしい。 何かを始めるのに、遅いことはない 移住して一番よかったと感じるポイントは? 「生きていくなかで大切なものに気づけたことでしょうか。自分らしさに気づかせてくれた家族や、いつも支えてくれる仲間たち。時間に追われる生活では、見えていなかったものが見えるようになりました。」 仕事の経験やスキル、人間関係など、年齢を重ねるほど積み重ねたものも多く、新たな人生を始めるには勇気も労力もいる。 「今ある暮らしをリセットして、新しい人生をスタートさせるのって大変です。でも、それ以上に得るものも大きいかもしれません。私の場合は、移住によって自分らしい豊かな暮らしを実現できました。経験者として言いたいのは、40代からでも全然遅くないよ!ということ。人生、まだまだこれからです。」 子育て支援センターや図書館、地域交流センター、カフェなどが入る複合交流施設の整備が進み、新たなまちづくりが進む真岡市。気になった方は、ぜひ真岡市の移住相談窓口へ。檜澤さんが真岡市の魅力をたっぷりと紹介してくれることだろう。