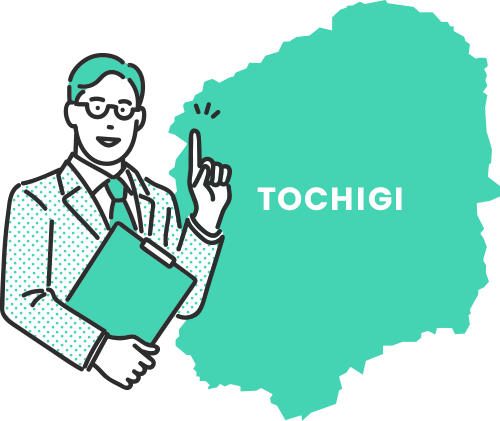“農”と“食”を通じて、地域を元気に
小鮒拓丸さん・千文さん
農業を生業にしたい。二人の思いが一つに 「こっちが10分加熱した“ゆずジュース”で、こっちが加熱していないものです。加熱時間や素材の配合などを少しずつ変えて、どのパターンが一番おいしいか、料理に合うかなど、来年度の商品化を目ざして試作を繰り返しているんです」 そう話す小鮒千文さんは東京で生まれ、3歳のころ父親の地元である福島県郡山市へ。“食”に関心を持ったのは、25歳のときに大きな病気をしたことがきっかけだった。 千文さん:「食べることは、生きることに直結している。食べ方や心のあり方が、健康であるためにはとても重要だと痛感しました。病気を機に『食を通じてみんなの元気を応援したい』と思い、食の勉強を始めたんです。マクロビオティックのスクールに通ったり、北京中医薬大学日本校で薬膳について学んだり、食について知れば知るほど、その根本である“農業”への関心が高まっていきました」 同じく郡山で生まれ育った拓丸さんは、人材派遣会社やアパレルのお店で働きながらも、だんだんと子どもの頃から好きだった動植物にかかわる仕事がしたいと考えるようになった。「農業を生業にしたい」と二人の思いが一致し、準備を始めたちょうどその頃、東日本大震災が発生した。 拓丸さん:「周囲で野菜の出荷停止が続く状況のなかで、農業を一から勉強し、就農するのは難しいのではないかと感じました。いろいろ調べた結果、千葉県の長生村にある会員制農園『FARM CAMPUS』を見つけ、社長さんの好意によって、住み込みで働きながら農業を学ばせていただけることになったんです」 千文さん:「震災後、郡山の保育園でも外遊びが制限されて、息子が保育園から脱走してしまったことがあったんです。息子をもう少しのびのびした環境で育てたいと思ったのも、移住を決めた理由でした」 仲間に支えられて農と食を学んだ、外房での日々 千葉県のFARM CAMPUSで、拓丸さんは農場長として働きながら、近隣の自然栽培を手がける農家にも通い、農業を学んでいった。 一方、千文さんは農園内にある古民家で「のうそんカフェnora(ノーラ)」を開店。郷土食をテーマに、地元の野菜やお米、魚などをいかした、この土地でしか食べられない料理を提供してきた。また、4年半過ごしたうちの最後の1年は、英語保育を手がける保育園で、離乳食から大人の食事まで毎日30人分の料理を手がけてきた。 千文さん:「農園の社長さんや移住者の仲間たちなど、たくさんの人の支えがあったからこそ、私たちは農業や食、カフェの運営などを学ばせてもらうことができました。独立にあたって、外房を離れるのはとても名残惜しかったのですが、これからは自分たちの足で歩んでいかなければいけないと思い、那珂川町での就農を決意したんです」 千葉から郡山へ帰省する途中、よく通っていた那珂川町。ここで暮らすことを選んだのは、里山や川の美しさにひかれたからだ。また、郡山の実家に近いことも大きな決め手になった。 里山の旬の恵みをおすそわけ 「あっ、ここにも顔を出していますよ!」 取材に訪れたのは、春の足音が聞こえ始めた頃。家の前に広がるフキ畑には、たくさんのフキノトウが顔を出していた。拓丸さんは地域の資源を活用しながら、10反(約3000坪)の畑で少量多品目栽培に取り組んでいる。春夏秋冬の旬な野菜をセットにし、直接東京や県内のお客さんに発送。地域の飲食店にも野菜を卸している。 拓丸さん:「これからは自分たちの野菜だけではなく、里山のタケノコやフキノトウ、地元のおばあちゃんがつくった梅干しや、製麺所が手がけた天日干しのそばなど、この地域に息づくいいものも一緒に届けていきたいですね。僕たちは里山でしかできない仕事を、都会に暮らす人はそこでしかできない仕事をして、お互いに足りないものを補い合って生活していく。そんな循環する関係を築いていくことは、この地域の産業や里山を守ることにもつながると思うんです」 食を通じて、地域の元気を応援したい 千文さんは地域おこし協力隊としてこれまでの食の経験をいかし、産前産後のお母さんを対象にした町のプログラムで、那珂川町の食材を使ったマクロビオティックランチなどを提供している。この取り組みが始まったのは、食を通じて何か役に立てることはないかと考えた千文さんが、自ら町の健康福祉課を訪ねたことがきっかけだった。「食事によって産前産後のお母さんの健康をサポートしていく」という考え方に担当者も共感してくれて、来年度からは毎月1回など定期的にランチを提供していく予定だ。 ゆずを活用した商品開発の取り組みも、自ら町の六次産業化部会に参加したことがきっかけでスタートした。 千文さん:「かつて那珂川町では新たな産業を生み出そうと、ゆずの木を植えたことがあったそうです。けれど、今では高齢化が進んで、活用されないまま放置されていました。このゆずをいかして、新たな商品をつくり出すのが目標です」 千文さんは、ゆずジュースやゆず紅茶、化粧水や入浴剤など、さまざまな製品を試作。来年度中の商品化を目ざしている。 “農”と“食”を通じて、地域に恩返しを 最後に、二人のこれからの夢についてうかがった。 千文さん:「いつになるかは分かりませんが、“食堂のおばちゃん”になるのが私の夢。那珂川町の豊かな食材をいかした料理を提供するような、いろんな世代の人が集う場所をつくれたらいいなって思っています」 拓丸さん:「いつか農園でも、新たな雇用を生み出していきたい。僕たちが外房で成長させてもらったように、那珂川町で農業を学んでみたい、移住したいという人を、一人でも多く応援できたらと考えています。もし那珂川町で農業をやってみたいという方がいたら、ホームページからなど、いつでもご連絡ください!」 二人は常に自分たちにできることは何かと考え、目の前にあることに一生懸命に打ち込んでいる。“農”と“食”という自分たちが学んできたことを、一つ一つ地域に還元していく。それこそが、子どもたちに少しでもいい地域を、世の中を残すことにつながると信じて。