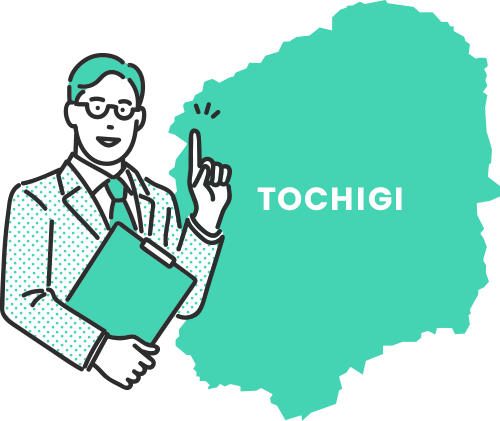つくることの楽しさを、子どもたちに
倉林真知子さん
一つとして同じものがない、作品との出会いを楽しんでほしい 布作家・倉林真知子さんのアトリエに一歩足を進めると、たくさんの色が目に飛び込んでくる。赤や青、黄緑など、ポップな色使いが、倉林さんの作品の魅力。さらに、問屋街を巡り探し出したデッドストックの布や革、古いボタン、さまざまな手芸店で入手した毛糸や刺繍糸など、素材の多くは一点もの。それによってつくられる作品は、どれもが世界に一つだけものとなる。 「例えば、ニット帽にアクセントとしてつけるタグやボタンの組み合わせ、つける位置なども、あえて少しずつ変えています。最近では木製の棒をカットして、ボタンも手作りしているんですよ。既製品のボタンのように均一な仕上がりではありませんが、逆に雑な感じが“味”になるんです」 さらに、アトリエではオーダーも受け付けている。例えば、バッグのデザインはそのままに、使う布の種類を変えてほしい、ここにポケットをプラスしてほしい、このボタンをアクセントにつけてほしいなど、自分だけの作品をつくってもらえるのだ。 「私の代表的な作品のひとつ『ループアクセサリー』(写真下)は、好きな糸の色や形をうかがって、その場で制作してお渡しすることもできます。アトリエに並んでいる作品は、あくまでも一つの提案。それをベースに、お客さん自身の遊び心も加えて、その方らしい作品を一緒につくれたらと思っています」 自分が楽しめてさえいれば、場所は関係ない 現在は布作家として活動する倉林さんだが、実は子どもの頃は手芸が苦手だった。 「それよりも、日曜大工が得意な父親の影響もあり、クギやトンカチが好きで、中学の頃から自分で机をつくったりしていました。手芸は苦手でしたが、色と色を組み合わせるのが大好きで、自然と洋服のコーディネートに興味を持つようになったんです」 東京の専門学校を卒業後、地元の下野市に戻り一旦は医療事務の仕事に就いたが、「やっぱり自分の好きなことを仕事にしたい」と、アパレル店に転職。販売の仕事を担当するも、強く興味をひかれたのはショーウィンドウのディスプレイや、店内全体をプロデュースする仕事だった。 もっとディスプレイや空間のコーディネートについて学びたいと、23歳で再び上京。最初に門をたたいたのは、知人が働いていた建築事務所。その後、横浜の帽子店で小物のディスプレイや見せ方の経験を積み、下北沢のシルバーアクセサリー店では、目標だった店内全体のコーディネートや、百貨店の催事に出店する際の企画、ディスプレイを担当。忙しくも、充実した時間を過ごした。 写真家と絵描きの友人と3人で、「ANT」の活動を始めたのもこの頃。倉林さんは、写真を撮影する際の洋服のコーディネートなどを担当。さらに布小物も制作し、イベントなどで販売していた。その当時からつくり続けているのが「鈴のアクセサリー」(写真上)。この作品が、栃木へ戻るきっかけを生み出してくれた。 「たまたま、宇都宮のイベントに出店していたとき、鈴のネックレスを宇都宮にある雑貨店『ムジカリズモ』のオーナーが目にしてくれて、『うちで作品を販売させてほしい』というお話しをいただいたんです」 当時は、ものづくりが自分の仕事になるとは、夢にも思っていなかった。 「でも、ムジカリズモさんに声をかけていただいたとき、これまで商品のディスプレイを考え、イベントの展示を企画し、宣伝なども手がけてきた経験は、そのまま自分のブランドを立ち上げても生かせるのではないかと思ったんです。また、『どこにいても、自分が楽しめてさえいれば場所は関係ない』と思えたことも大きかったですね」 こうして倉林さんはANTとして本格的に活動するために、栃木に戻る決意をした。 前に進むためには、つくりたいものをつくること 2004年に、下野市の実家にUターンした倉林さんは、両親に「1年でなんとかする」と宣言。その言葉どおり、1年後にはものづくりの仕事だけで暮らしていけるようになった。 「当時は、朝起きてから夜寝るまで1日中、制作していました。でも、全然苦ではなくて。自分の好きなことを仕事にするために、全力をかけて頑張りたかったんです」 作品をつくるうえで大切にしているのは、とにかく自分が楽しむこと。 「制作が義務になってしまうと、きっと何も生まれなくなってしまう。だから、自分がつくりたいもの、身に付けたいものをつくることが根本にあります。もちろん、個展の前や毎年参加している益子の陶器市の直前には、制作に追われて楽しいアイデアが出てこなくなることもある。そうならないためにも、あえて『自由に制作する日』を設けるようにしているんです」 作品のインスピレーションはどこから? とたずねると、「最近は、絵本や写真集からが多いですね」という意外な答えが返ってきた。 「絵本のなかで配色が美しいページだったり、写真集で外国のカラフルな街並みだったりを見ると、その色使いを作品で表現したくなるんです。色の組み合わせが大好きなのは、子どもの頃から変わらないですね。作品をつくるうえで、これまでのディスプレイや空間のコーディネートなど、すべての経験が役立っています」 この場所だからこそ始まった、ものづくりイベント 結婚後は、宇都宮の街中にあるご主人の実家でしばらく暮らしていたが、子育てを考え、より自然が身近なさくら市へ。ご主人の親戚の生家で、10年ほど空き家になっていた古民家の味わいある雰囲気が気に入り、自宅兼アトリエに選んだ。ここへ移り住んでよかったのは、周囲に自然が多いのどかな環境でありながら、幼稚園や小中学校、塾をはじめ、スーパーや病院など、生活に必要なお店や施設が近くにそろっていること。移動に時間を取られることがないため、その分を作品づくりに充てることができる。 さらに嬉しいのは、やはり自然が身近にあることだ。 「私たち家族は外遊びが好きで、週末には公園にシートと編み物セットを持っていって、息子を遊ばせながら、私はシートのうえで編み物をしたり、本を読んだりしています。地域のみなさんは温かく、子どもを見守ってくださるので、安心して外で遊ばせることができます」 自宅の前には大きな庭があり、息子さんは泥んこになりながら、虫を捕まえたり、葉っぱを拾い集めたり、外遊びを満喫している。その姿を見て生まれたのが、「にわのひ」というイベントだ。「家に閉じこもってゲームなどをするのではなく、子どもたちに自然の中でものづくりを楽しんでほしい」との思いから、自宅の庭に信頼する作り手を招き、ワークショップを中心としたイベントを毎月開催。今ではさくら市の後援を受け、氏家駅前広場などで実施している。さらに、2015年からは毎年夏に、さくら市ミュージアム勝山公園で「もりのひ」というイベントも行っている。 「『もりのひ』では作家さんたちが出店するブースやゲート、看板なども、身近な素材である段ボールを使って、みんなで手作りしています。そのコンセプトは、『にわのひ』と変わりません。これからもANTの活動と並行して、子どもたちにものづくりの楽しさを届けていけたらと思っています」 (↑ 2016年11月に開催された「にわのひ」のDM写真。男の子は、いつも倉林さんのアトリエの庭や、「にわのひ」などのイベントに出店している、「WANI Coffee」の店主の息子さん)